膨大な通常業務に追われる中、社内から頻繁に入るイレギュラーな問い合わせと、頭が混乱するほどの激務でありながら、ミスは許されない総務部。このような状況を他部署の人間は誰も理解してくれず、ストレスはたまる一方です。
AIチャットボットを導入して、新しい総務の形を目指してみませんか?
総務の仕事は非常に幅広く、また細かい作業も多いことから、仕事を進める上で様々な課題に直面します。総務の主な困りごとを3点ほど見てみましょう。
総務は属人化・業務のブラックボックス化が起こりやすい部署といわれています。理由は、一般的に総務はギリギリの人員で運営されているためです。
間接部門たる総務は、会社全体においてコスト削減の対象になりやすい部署です。コスト削減のために削られた少ない人員で業務効率化を図るためには、特定の個人が特定の仕事を担当する形が深化していくことがあります。業務の属人化・ブラックボックス化が起こることは、当然かもしれません。
総務スタッフは、他部署から想定外のタイミングで想定外の業務をお願いされることが多々あります。社内の他部署にとって、総務は漠然と「なんでも屋さん」と思われがち。そのため、「何か困ったら総務にお願いしよう」という社員が少なくないためです。
しかしながら、いかに総務とはいえ即対応できる業務は限られています。自分の知らない業務がイレギュラーなタイミングで入れば、本来行うべきコア業務が圧迫されてしまいます。
社員1人あたりの仕事量は膨大であるにも関わらず、基本的に総務には一切のミスも許されません。他部署では、「自分がミスをしていても、最後は総務が気づいてくれる」と思っている社員が多くいます。
社内のあらゆるミスを食い止める最後の砦と認識されていることから、総務スタッフの神経は常に疲弊しています。
上記のような課題を抱えている総務の方は、AIチャットボットを導入してみてはいかがでしょうか?AIチャットボットを総務に導入すれば、主に次のようなメリットが生まれます。
他部署から総務への問い合わせ内容の多くは、休暇取得申請や旅費精算などの定型的なものがほとんどです。AIチャットボットでも対応可能なものが大半です。
あらゆる問い合わせを一旦AIチャットボット経由にすれば、総務へ直接入る問い合わせ件数の激減が期待できるでしょう。
社内からの問い合わせ件数が減れば、総務の業務負担は大きく軽減します。
イレギュラーな問い合わせへも対応する余裕がうまれるため、より健やかな心持ちでコア業務に臨めることでしょう。
AIチャットボットの導入で、総務のコスト削減につながる可能性があります。
問い合わせ対応に追われながら、時期によっては、とても尋常とはいえない業務を遂行する総務スタッフ。会社にとって、総務の残業代は決して安くありません。業務が多忙なため離職リスクもあることから、新規採用や教育にかかるコストも想定しておく必要があります。
総務が忙殺から開放されれば、これらコストの削減につながる可能性が高いでしょう。
AIチャットボットは自己学習をするツールですので、社内からの様々な問い合わせに対応する過程で、徐々にナレッジを蓄積していきます。
使えば使うほど能力がブラッシュアップされ、優秀な一社員のごとくに成長する可能性もあるでしょう。
AIチャットボットは、24時間365日、いつでも総務の片腕として働きます。そのため、他部署との就業時間の違いにより総務スタッフが直接対応できないときでも、他部署の社員は総務のAIチャットボットで多くの問題を解決させられます。
総務でAIチャットボットを利用する際の主なポイントを3点ほど見てみましょう。
総務によく寄せられる質問については、あらかじめ質問内容と正しい回答をAIチャットボットに学習させておきましょう。関連して寄せられそうな質問についても、先んじて学習させておくようおすすめします。
これらの初期設定は、AIチャットボットが自己成長する上で大事な土台となります。
AIチャットボットに正しく回答させるため、定期的なチューニングは欠かせません。
チューニングとは、想定外の質問や表現などのデータを収集し、これらに合わせて正しく回答するよう繰り返し学習させる作業のことです。特に学習量の少ない導入当初は、こまめにツールを使ってチューニングを行うようにしましょう。
利用者が求めている回答の選択肢が示されない場合、利用者はAIチャットボットから途中で離脱することがあります。離脱頻度が多くなれば利用者の満足度は下がり、再び総務への問い合わせが増加するでしょう。
このような事態を避けるためには、利用データを分析して離脱箇所を特定し、都度AIチャットボットに適切な学習をさせることが大事です。
初めてAIチャットボットを導入する場合には、スムーズに初期設定が完了するよう手厚いサポートが必要です。また、導入後に問題が生じた際にも速やかに解決を図れるよう、継続的なサポート体制のある製品を選ぶようにしましょう。
チャットボットにはAI非搭載のタイプもありますが、利用者からの質問を通じて自己進化を促すためには、AI搭載タイプを選ぶ必要があります。
AI非搭載タイプを選ぶと総務の業務効率化は限定的になってしまいます。誤ってAI非搭載タイプを選ばないよう注意しましょう。
導入に際しては、使い勝手や機能性等を確認するため、無料トライアルを試してみましょう。いかに評判の良い製品であっても、無料トライアルを割愛して導入を決めることはおすすめできません。もとより、無料トライアルを用意していない製品は選択肢から外したほうが良いでしょう。
昔から総務の仕事は得てして激務です。AIチャットボットの登場で、今やそんな時代も大きく変わろうとしています。全ての企業の総務において、一刻も早くAIチャットボットが導入されるよう願うばかりです。
メールや電話、口頭での確認…。ちょっとしたことなのに、対応や案内に時間がかかる。その積み重ねが、気づけば大きな業務ロスにつながっている。そんな「社内コミュニケーションのムダ」をスマートに変える手段として、チャットボットが注目されています。ここでは、用途別に選べる「社内チャットボット3選」をご紹介。単なる便利ツールではなく、日々の社内業務に「変化」をもたらすきっかけとして導入を検討してみませんか?

引用元:NDIソリューションズ
https://solution.ndisol.jp/cb3

引用元:TDSE
https://cognigy.tdse.jp/
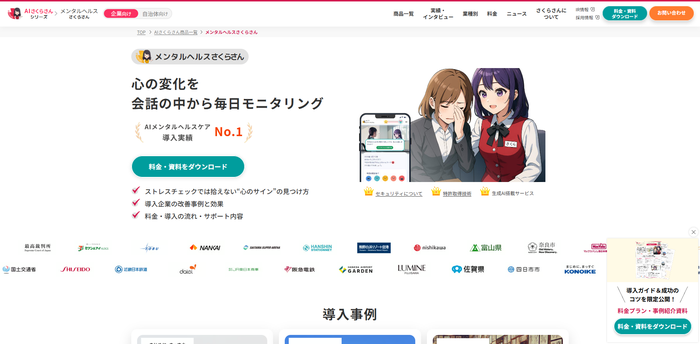
引用元:サンソウシステムズ
https://www.tifana.ai/products/mental