技術の発展や働き方改革などの背景から、AI技術がどんどん身近になっています。ここではその中でも「AIチャットボット」に焦点をあて、仕組みや種類を解説します。有効活用するためにも、まずは仕組みを理解しておきましょう。
チャットボットの仕組みには大きく「AI型」と「シナリオ型」があり、それぞれ仕組みが異なっています。ここではそれぞれの違いについて紹介・解説しますので、ぜひチェックしていって下さい。
「AI型」はその名の通りAIが回答を行うチャットボットであり、初期設定の際に読み込ませた膨大なデータに加え運用しながら学習を重ねて得たデータも踏まえながら、ユーザーの質問に対して最適と思われる回答を行います。AIの性質として保有・蓄積しているデータが増えれば増えるほど受け答えの精度が高まっていき、自然な応答・会話が可能になります。一方でデータのボリュームと質が不十分であれば、精度の低い回答になってしまう点には注意が必要です。
シナリオ型のチャットボットは「ルールベース型」とも呼ばれており、シナリオと呼ばれる会話のフローをあらかじめ設定することで想定される質問と回答をセットで準備して会話を行います。AI型に比べると安価で導入しやすいという特徴がありますが、シナリオにおいて想定される質問は正確に回答できる反面「シナリオ外の質問には回答できない」という弱みのある形式です。よくある質問やFAQのようなパターン化しやすい質問対応には適している形式であるといえるでしょう。
大きく2通りあると紹介したチャットボットですが、そこから更に4タイプに細分化することが可能です。これらの仕組みを理解しておくと、より目的に合致したチャットボットが構築できるでしょう。順に紹介していきます。
選択肢タイプはその名の通り選択肢から質問を選び、該当する回答を表示する仕組みのチャットボットです。決められたシナリオに沿って選択式で対話を進めて行く形式になっていますので、ユーザー側は設定されたシナリオ(回答)から適したものを選択します。質問への回答・対応としては最適なものが表示される形式ではありますが、シナリオに無い受け答えをすることはできません。
ログとは会話・対話の履歴を意味しており、チャットボットにおいてログタイプのものは会話のログを蓄積することで文脈に応じた会話を行うことができるようになります。大量のログをどんどん蓄積することができれば、その膨大なデータから機械学習が加速しより人間に近い(人間らしい)会話ができるようになります。近年の技術ではログとして蓄積されたものをさらに解析し、自然な会話ができるようどんどん成長していく仕組みが確立されつつありますので、その会話データを集めるという点も重要なポイントになっています。
ハッシュタイプは「辞書タイプ」とも呼ばれる形式のチャットボットであり、辞書内に登録されたテンプレートをベースに対話・会話を進めて行くことになります。会話を行う事ができる範囲は限定的になりますが、範囲内であれば受け答えをスムーズに行うことが可能という特徴があります。選択肢タイプよりは会話・選択の幅が広くなりますがログタイプほどの柔軟さはないというちょうど両タイプの中間あたりに位置する形式となっています。
チャットボットにおける「Eliza タイプ」は、チャットボットの原型になった「Eliza (イライザ)」から名付けられた形式となっています。基本的には聞き役に徹するボットとなっており、あいづちによって返答や言葉の要約を行い、聞き返しながら会話を進めて行きます。この原型になったElizaは1966年に誕生したソフトウェアであり、チャットボットの起源としても広く知られています。あたかも本当の人間と会話しているかのように感じさせる返答が特徴で、対話に夢中になる状態を「イライザ効果」と呼ぶこともあります。
AIの特徴は「機械学習」というその名の通り、日々学習をしてクオリティが上がっていく点にあります。この学習は「ディープラーニング」とも呼ばれており、人間の脳にある神経細胞を模してシステムを作ろうとする動き・技術のことを意味しています。人がパラメータの設定を行うのではなくコンピュータ自身が学習を行うという点が今までの技術と明確に異なっており、今後もさらなる性能向上が期待されています。特にチャットボットの開発においてはビッグデータと呼ばれる膨大な量の情報を参照し、会話の法則やルールを徹底的に学習させています。これによりどんどん自然なチャットボットへと成長していき、自らで文脈を組み立てて回答できるようになっていきます。
一言でAIチャットボットといってもその種類はこのページで紹介したようにさまざまなものがあります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがありますので、仕組みを理解したうえで目的に合うものを選ぶようにしましょう。
メールや電話、口頭での確認…。ちょっとしたことなのに、対応や案内に時間がかかる。その積み重ねが、気づけば大きな業務ロスにつながっている。そんな「社内コミュニケーションのムダ」をスマートに変える手段として、チャットボットが注目されています。ここでは、用途別に選べる「社内チャットボット3選」をご紹介。単なる便利ツールではなく、日々の社内業務に「変化」をもたらすきっかけとして導入を検討してみませんか?

引用元:NDIソリューションズ
https://solution.ndisol.jp/cb3

引用元:TDSE
https://cognigy.tdse.jp/
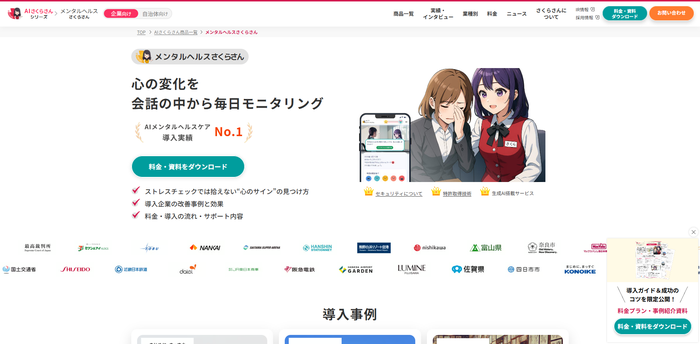
引用元:サンソウシステムズ
https://www.tifana.ai/products/mental