生成AIの回答精度を高められる技術として、注目されているRAG(検索拡張生成)を解説しています。どのような技術なのか、また導入するメリットや注意点、活用例をまとめました。
生成AIの一部であるLLM(大規模言語モデル)の回答精度を向上させる技術を、「RAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)」といいます。この技術では、LLMの情報と外部情報を組み合わせることによって、正確性の高いテキストの生成が可能になります。
具体的な仕組みとしては、LLMが回答を生成する前段階にて外部の最新情報を検索し、そこで得られた情報を回答に反映させます。RAGは、これまで生成AIによる回答で課題となっていた、「事実と異なる内容の回答が生成される」「文脈と無関係な出力がもっともらしく生成される」などのリスクを改善するために、有効な技術として注目されています。
RAGの処理は、大きく分けると「検索」と「生成」の2つのフェーズに分けられます。
まず、ユーザーが生成AIに質問を入力するとRAGがその内容をもとにして検索を行います。RAGは主に企業が保有する内部データベースやインターネット上の最新の情報を活用します。そして検索により取得された情報をもとにして、LLMがユーザーの入力に対してテキストの生成を行います。ここでは、まずユーザーの質問と検索段階で取得した情報を統合し、テキストを生成してユーザーに返す流れになります。
このように、RAGは大量のデータの中から関連する情報を取り出し、その情報をもとに新しい回答を生成することが可能になります。
上記でも少しご紹介していますが、生成AIには事実と異なる内容の回答が生成される「ハルシネーション」のリスクがあります。しかしRAGは用意されたデータベースからAIが情報を探して回答を返すため、回答元の情報管理が可能となります。用意するデータベースの内容が正しいものであれば、誤った情報を回答をしないように調整することも可能です。
また、もし情報が見つからない場合には、「答えが見つからない」という内容を返すことができ、事実と異なる内容の回答が提示されるリスクも減らせます。
生成AIは、インターネット上に公開されている情報をもとにした回答を行うため、公開されていない情報に関するやりとりが行えません。そのため、企業における組織固有の情報を使用して、社内の問い合わせや顧客分析を行うといった処理には対応できないことになります。さらに、生成AIツールによっては最新の情報を学習していないものもあります。
上記の点に対し、RAGはデータベースに登録されている情報に基づき回答を生成します。この点から非公開の情報や最新の情報をデータベースに登録することで、AIもさまざまな情報を扱えるようになります。
情報検索を行うため、生成AIと比較した場合RAGは回答を提示するまでに時間がかかることがあります。また、データベースの情報量が多いと、それだけ検索にかかる時間も長くなります。ユーザーは「すぐに回答が欲しい」と考えていることも多いと予想されるため、回答までに時間がかかりすぎるとユーザーの満足度が下がる可能性も。例えば顧客問合せにRAGを活用しようとする場合には、あまりにも回答に時間がかかると見込み客を逃す可能性も考えられます。
この点については、データベースに登録する情報を絞り込むことが対策として挙げられます。また、あらかじめ「回答までに時間がかかるケースがある」と明記するのも対策のひとつといえます。
ここまでご紹介してきた通り、RAGはデータベースを参照した上で回答を生成するため、データベースに登録されているデータの質によって回答の精度が左右される点には注意が必要です。もし情報が間違っている場合には、当然生成される回答も間違ったものになってしまいます。
誤った回答を返さないためにも、データベースに登録されている情報は定期的に更新し、新しい情報を参照できるようにしておくことが大切です。
ビジネスの現場において、RAGはさまざまな形で活用されています。
例えば、自社で提供している製品やサービスの情報をデータベースに登録した場合、カスタマーサポートで活用が可能です。RAGを導入し、そこで顧客からの問合せに対応できれば、電話やメールなどで問い合わせる必要がなくなるため、顧客満足度のアップも期待できますし、問い合わせに対応のコスト削減も可能です。
そのほかにも、「社内問い合わせへの対応」や「営業資料やメールなどの生成」「さまざまなデータを活用した分析」のように、RAGは多彩な形で使用されています。
こちらの記事では、RAG(検索拡張生成)の概要や導入メリット、導入にあたっての注意点、活用例などをご紹介してきました。RAGは、生成AIにおいてこれまで課題とされていた点を補い、さらにビジネスに活用することで業務の効率化が期待できる技術です。さまざまな活用方法が考えられるため、業務の効率化を図りたいと考えている場合には、このRAG技術をチェックしてみてください。
メールや電話、口頭での確認…。ちょっとしたことなのに、対応や案内に時間がかかる。その積み重ねが、気づけば大きな業務ロスにつながっている。そんな「社内コミュニケーションのムダ」をスマートに変える手段として、チャットボットが注目されています。ここでは、用途別に選べる「社内チャットボット3選」をご紹介。単なる便利ツールではなく、日々の社内業務に「変化」をもたらすきっかけとして導入を検討してみませんか?

引用元:NDIソリューションズ
https://solution.ndisol.jp/cb3

引用元:TDSE
https://cognigy.tdse.jp/
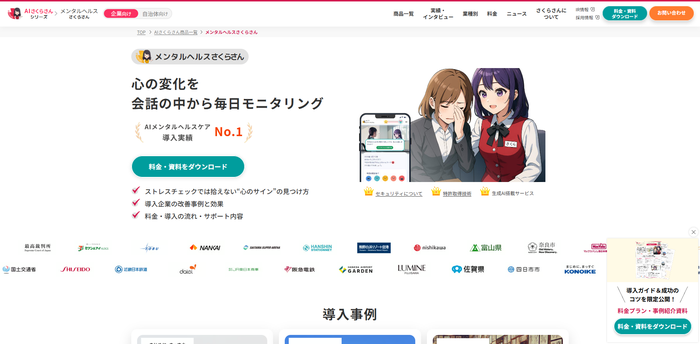
引用元:サンソウシステムズ
https://www.tifana.ai/products/mental