会社の業務をより効率的に進められるようにすることを目的に、社内向けチャットボットの導入を検討している方に役立つ情報をまとめました。失敗事例や費用対効果、そして有効利用するための方法などについてみていきましょう。
ある大企業の人事関連セクションで、業務負担軽減のためにチャットボットを導入した事例です。導入当初は、一定数の社員が利用していたのですが、徐々に利用者数が減っていきました。そして、結果的には利用中止になってしまいました。
【なぜ利用者が減った?】
チャットボットの利用中止という結果に終わってしまった原因として挙げられるのは、FAQやフローを増やし過ぎたことです。数が多ければその分便利になるように思われるかもしれませんが、実際には、利用する際の選択肢も多くなりすぎてしまうのです。その結果、求めている回答にたどりつくまでに時間がかかるようになったのです。
ある企業では、増大したデータの情報検索をスムーズに行うためにチャットボットを導入。営業資料の検索や業務手続きの効率化が可能になるようビッグデータと連携させて、データベース化しました。けれども、思うように情報を得られなかったため、実際にはあまり利用されることがなかったという事例です。
【なぜ情報を得られなかった?】
社員が求めている情報や、情報を得る目的などが明確化されていなかったことが、おもな問題であったと考えられます。ニーズを充分に把握した上で、KPI設定をすることが欠かせません。
あまり使い勝手の良くないチャットボットを導入してしまった事例です。チャットボット未経験者やITリテラシーが高くない社員が多い職場では特に、操作すること自体が負担に感じられてしまいます。そうなると、業務効率化のために活用するのは困難です。
【なぜ使いにくい?】
使いやすいUI・UXのチャットボットでないと、操作に慣れるのにも苦労してしまう場合があります。使い勝手が良いチャットボットの例としては、自然文検索に対応可能なAI搭載タイプや、求めている情報をサジェストしてくれる機能が搭載されているタイプなどが挙げられます。
AI搭載タイプの機械学習型チャットボットを導入したものの、すぐに活用することができなかったという事例です。機械学習型は、一定以上の期間にわたり、回答の精度を向上させるための学習が欠かせないのです。ですから、導入後すぐに業務をパワフルにサポートしてくれることを期待して導入してしまうと、その期待が裏切られたように感じてしまいます。
【導入前にしておくべき用意は?】
学習リソースやメンテナンス用リソースを準備しておくことが大切です。そうでないと、導入後、スムーズに学習期間に移行することができないからです。
ただ、毎週数時間以上を学習時間に充てたにもかかわらず、その効果がみられない場合は、別の問題がある可能性についても考慮に入れる必要があります。
チャットボットは、業務の効率化に力を発揮してくれる便利なツールではありますが、初期費用やランニングコストがかなりかかってしまうことも。あまりにも高額なものを導入してしまうと、費用対効果が合わなくなります。充分なコストメリットがあるかどうかについて、じっくりと検討した上で導入するか否かを判断することが大切です。
効率化したいと考えている業務内容に適していないチャットボットを選んでしまうと、上手く活用できません。例えば、チャットボットには、カスタマーサポートに特化されているものもあり、それを社内スタッフ用として使おうとしても、思い通りに役立てることは難しいでしょう。
さらに、AIの有無についても事前に確認してくことが大切です。AI非搭載のチャットボットは、問い合わせ内容の種類が少ない場合にはとても便利です。一方、AIが搭載されているタイプは、幅ひろい問い合わせ内容に臨機応変に対応できるような設計になっているものが多いです。用途をふまえて、適したチャットボットを選択するようにしましょう。
必要なFAQが登録されていないと、業務に役立てることは困難です。チャットボットは登録されているFAQについての問い合わせに対応するためのツールなので、未登録の問い合わせ内容に回答することは不可能です。
回答できなければ、結局は、メールや電話など、ほかの方法で問い合わせざるを得なくなってしまいます。チャットボットから回答を得られないことが続けば、利用する社内スタッフはおのずと減っていってしまうでしょう。
導入後に必要なFAQを登録しておいたとしても、それ以降に分析やメンテナンスをしなくなってしまえば、やがて回答内容が不充分になったり、あるいは情報が古くなりすぎたりするなどの支障が生じます。回答の質が低下してしまうと、業務効率の向上につなげることは難しくなります。
そういった事態になるのを避けるためにも、できれば導入前に、チャットボット運用業務のためにリソースを割くことのできる社内スタッフを確保できるかどうかを、確認しておくことが求められます。
業務に適したタイプのチャットボットを選び、さらに充分なFAQ登録の上、適切に運用をしていたとしても、社内スタッフへの周知が充分でなければ、役立てることはできません。
必要な情報を網羅しているチャットボットであっても、利用されてはじめてその力を発揮します。初期費用や運用コストを無駄にしないためにも、しっかりとチャットボットの存在を知ってもらうことが重要です。
AIが搭載されているチャットボットを導入する際は、応答精度が高くなるように運用していくことが大切です。なかでも、機械学習型の場合には、AIの学習用データを登録したり回答の正誤の評価をしたりして、精度を高めていく必要があります。精度が低いままでは、求められている情報を回答できない可能性があります。
メールや電話、口頭での確認…。ちょっとしたことなのに、対応や案内に時間がかかる。その積み重ねが、気づけば大きな業務ロスにつながっている。そんな「社内コミュニケーションのムダ」をスマートに変える手段として、チャットボットが注目されています。ここでは、用途別に選べる「社内チャットボット3選」をご紹介。単なる便利ツールではなく、日々の社内業務に「変化」をもたらすきっかけとして導入を検討してみませんか?

引用元:NDIソリューションズ
https://solution.ndisol.jp/cb3

引用元:TDSE
https://cognigy.tdse.jp/
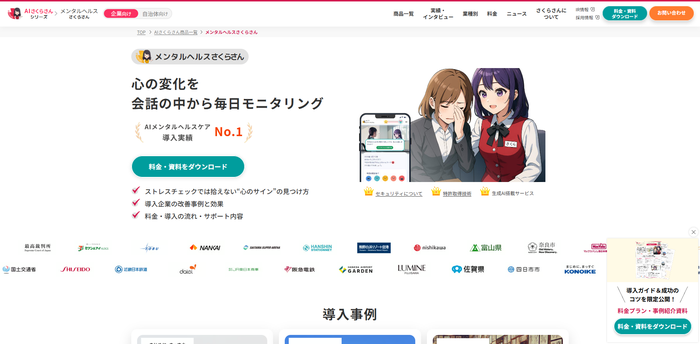
引用元:サンソウシステムズ
https://www.tifana.ai/products/mental