社内でチャットボットの導入を検討するにあたり、知っておきたい知識をまとめました。各ページでは、より詳しく紹介しているので、合わせてご確認ください。
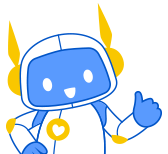
当サイトでは、コストと導入・運用負荷の軽減に着目しチャットボットの選び方を解説。忙しい人事・総務、情報システムやDX推進担当の方がチャッと!自社の状況にあったチャットボットを選べるように、担当別の要望に合わせておすすめの製品を紹介しています。
チャットボットとは、ユーザーと自動で会話を行うプログラムのことをいいます。チャットにボット(処理を自動実行するプログラム)を組み合わせた造語で、カスタマーサービスや予約システムなど、幅広い分野で取り入れられています。
また、社内向けチャットボットの利活用も進んでおり、導入すれば問い合わせ対応を自動化したり、FAQシステムを構築したりできます。
チャットボットは、大きく分けて2つの種類があります。
AI型は、人工知能が搭載されているチャットボットです。ユーザーからのメッセージに対して、AIが学習データを元に適切な返答を提示します。複雑な内容の質問にも対応が可能で、後述のシナリオ型と比べて回答の精度が高めです。また、AIにユーザーの質問データなどを学習させることで、より回答の精度を高められます。
シナリオ型は、ユーザーの問い合わせに対して特定のアンサーを提示するチャットボットです。ユーザーは複数の選択肢の中から自分に合ったものを選ぶと、チャットボットが選択肢に沿った返答を行います。いわゆる「よくある質問」のように、定型文を返答する際に適しています。また、簡単に設置・運用できるため、AI型と比較してコストを抑えられます。
社内にチャットボットを導入した場合、バックオフィス部門の効率化や生産性向上につながります。問い合わせ業務が自動化されますので、有人対応の件数を減らし、担当者の負担を軽減できるでしょう。また、属人化の防止にも寄与するほか、問い合わせ対応に必要な人員を減らせることから、バックオフィス部門のコストを削減できる可能性もあります。
チャットボットを設置する際は、初期費用と月額費用が発生します。初期費用は無料のツールも多い一方、月額費用はツールによって異なります。特にAI搭載の有無で大きく変わりますので、チャットボットの種類は慎重に検討を進めましょう。また、カスタマイズ費用やオプション費用にも注意する必要があります。
チャットボットの仕組みは大きく2種類に分けられています。1つはAIが回答を行う「AI型」のもの、もう1つがシナリオと呼ばれる会話のフローをあらかじめ設定して回答を行っていく「シナリオ型」です。この2つもさらに細分化することができます。
「AI」とはコンピュータにより人間の知能を再現する技術のことを指します。また、自動でチャットを行うプログラムを「チャットボット」と呼びます。そして、「AIチャットボット」とは、学習したAIにより入力された質問に対して回答を行うプログラムのことです。
AIチャットボットは非常に便利なツールであるものの、実はさまざまな危険性が潜んでいます。あらかじめどのような危険が考えられるのかを知っておき、必要に応じて対策を行っていくことが重要なポイントになってきます。
チャットボットの自作には、「プログラミングによって一から自作する」「フレームワークやAPIを活用する」といった方法があります。一から自作する場合は高度な技術や専門知識が求められるため、人材の確保も必要です。また、公開後の調整やトラブル処理も自社で行わなければいけません。
シナリオ型チャットボットは、あらかじめ作成したシナリオに沿って回答する方式をとります。比較的低コストで導入・運用できるうえ、提示された選択肢から選んで回答を得るため気軽に利用しやすいというメリットも。ただし、シナリオ通りの回答しかできず、想定外の質問には回答できないというデメリットもあります。
チャットボットを導入する際は、導入目的をはっきりさせます。何を求めているか、また設置場所はどうするかを整理しましょう。複数あるチャットボットツールやベンダーを比較し、無料トライアルも活用してみるのがおすすめです。シナリオ作りや運用体制を整えたうえで導入しましょう。
コーパスはデータベースのことです。AIはコーパスを活用して言葉を生成します。また、コーパスは自然言語を機械が処理して抽出する技術である、自然言語処理が必要です。コーパスは膨大な情報量と自然処理技術により、人の話し言葉まで含めて解析します。
チャットボットを活用して業務の効率化を実現するためには、導入前に失敗事例や失敗の原因などを参考にしながら、じっくりと検討しておくことが大切です。また、費用対効果の観点から、初期費用とランニングコストについても計算に入れておく必要があります。
業務効率化にどのくらい影響しているかを適切に測定するために、前もってチャットボットの目標設定をしておくようにしましょう。その上で、測定期間や測定方法などを検討していきます。また、測定後には、今後につながる改善施策についても考えておくことが大切です。
近頃、生成AIの回答精度を高めるための技術として、RAG(Retrieval Augmented Generation:検索拡張生成)が注目されています。これまで生成AIの課題とされてきたハルシネーションのリスクを低減できること、また回答元となる情報管理が可能などのメリットがある技術です。この技術はカスタマーサポートや社内問い合わせ、各種分析などビジネスの現場でもさまざまなシーンで活用することができるため、導入により生産性の向上などが期待できます。
チャットボットと有人チャットの違いを解説します。自動対応が得意なチャットボットと、柔軟な対応ができる有人チャット、それぞれの特徴やメリットを理解し、どのように併用することで効果的な顧客サポートが可能になるかを説明します。
チャットボットが持つポテンシャルを最大限に引き出すためには、会話デザインが重要です。ユーザーのニーズに即したシンプルで直感的なフロー設計を行うことで、利用者がスムーズに問題を解決でき、満足度を高めることができます。さらに、応答の限界を認識し、適切に有人対応へエスカレーションすることで、より良い体験を提供します。
多言語対応チャットボットの導入は、社内外のコミュニケーション効率を大幅に向上させる手段です。しかし、翻訳の質や対応可能な言語の数など、課題も少なくありません。外国人顧客や労働者へのサポート、グローバルビジネス支援など、導入前に多様な利点について知っておきましょう。
チャットボットとGPTは、それぞれ異なる特徴を持つ対話型ツールです。チャットボットは、事前に設定されたルールやシナリオに基づいて、特定の質問への正確な応答やタスクの自動化を行います。一方、GPTは高度な自然言語処理技術を活用し、幅広いトピックに柔軟に対応し、人間らしい文章を生成する能力を持ちます。ここでは、導入時に役立つポイントや併用する際のメリットを紹介します。
ボイスボットは自然な会話体験と柔軟な対応が可能ですが、音声認識精度に課題があります。チャットボットは24時間即時対応が可能で、多言語対応にも優れますが、複雑なケースには不向きです。一方、IVRは信頼性とコスト効率に優れていますが、ユーザー体験や柔軟性に限界があります。これらの違いを理解し、適切な場面で活用することで、業務効率の向上と顧客満足度の向上を実現できます。
自治体がAIチャットボットを導入する背景には、住民サービスの向上や業務効率化への期待があります。具体的な導入事例を交え、メリットや課題、成功の鍵を詳しく解説します。
AIチャットボットの解約手順や注意点を詳細に解説。具体的な手続きの流れ、タイミングの重要性、データ管理、解約後のサポートを説明します。
チャットボットは、ユーザーの質問に対して自動で返答してくれる便利なシステムです。問い合わせ対応を始め、さまざまな業務に活用できます。なお、AI型とシナリオ型があり、いずれもオフィスの業務改善に寄与するでしょう。
メールや電話、口頭での確認…。ちょっとしたことなのに、対応や案内に時間がかかる。その積み重ねが、気づけば大きな業務ロスにつながっている。そんな「社内コミュニケーションのムダ」をスマートに変える手段として、チャットボットが注目されています。ここでは、用途別に選べる「社内チャットボット3選」をご紹介。単なる便利ツールではなく、日々の社内業務に「変化」をもたらすきっかけとして導入を検討してみませんか?

引用元:NDIソリューションズ
https://solution.ndisol.jp/cb3

引用元:TDSE
https://cognigy.tdse.jp/
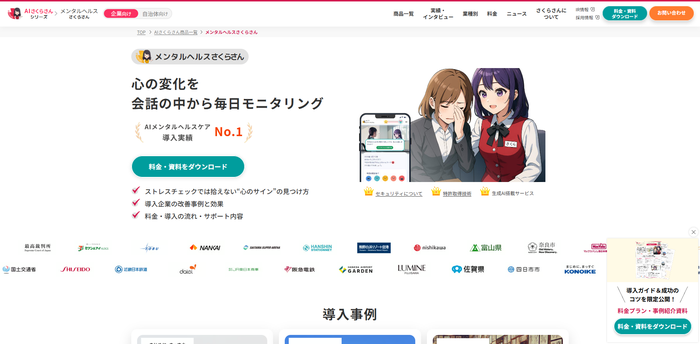
引用元:サンソウシステムズ
https://www.tifana.ai/products/mental